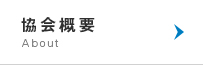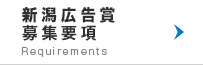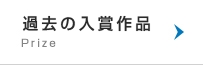お知らせ
「燕三条 工場の祭典」開催に先がけ 見学



昨年10月、本県のものづくりのメッカ「燕三条」地区で開催され、5日間で1万人以上が訪れた注目のイベント「燕三条 工場の祭典」。今年も10月2~5日に開催されるのに先立ち、協会メンバー20社34人で見学に伺ってきました。
最初の見学先は三条市の近藤製作所様。創業100年の鍬メーカーです。工場に近づくと、トントントントンと、機械で鋼を叩き成型している音が。黒光りする重々しい工作機械が並ぶ中、作業服姿の社長さんがにこやかに出迎えてくださり、製造過程など説明を聞きました。販売先は全国各地におよび、土地によって全く形が異なるんだそう。「父の代は、鍬は高価なものだったので近所の農家に貸して代わりにコメや野菜をもらっていました。今は全国からの受注生産のほか、修理の注文が多いですねえ」と近藤社長。傍らで鋼を切断していたのは社長の奥様。「退職記念にオリジナルの鍬を作る方もいらっしゃいます。この前は、彼女へのプレゼントにと若い人が注文してくれましたよ」と聞かせてくださいました。同社の後継者は30代の息子さん。農業への関心が高まる今、2世紀目を迎える老舗に新しい風が吹き始めているように感じました。




次におじゃましたのは、鎚起銅器で有名な燕市の玉川堂様。昭和の初めの築という30畳ほどの畳敷きの作業場では、職人さんが黙々と、リズミカルに銅板を鎚で叩いてグラスなど制作中。20代の方も数人いらっしゃいますが、最初は錫での表面処理や色の仕上げの作業を担当し、叩くのは2年目以降とのこと。技術習得のため、自主特訓もあるようです。とかく高価なイメージの鎚起銅器ですが、叩いてはなますを20回も繰り返すという作業を拝見するにつけ「納得…」の一言でした。近年は東京や海外にも販路を広げる同社ですが、「人気のあるのは、デザイナーさんよりも昔ながらの職人がデザインしたものなんです」と話す45年のベテラン、細野五郎さん。静かですが誇りに満ちた語り口がとても印象的でした。
この日、2社に案内して下さったのは三条市商工課の澁谷一真主任。地元の取り組みを理解してもらおうという真剣なまなざしに、海外からも評価されているというこの催しの成功と魅力の一因を感じました。人が地域を作っている、改めてそのことの大切さを学んだ気がします。
昨年は4割が県外客だったという「工場の祭典」。見学後、履歴書を持って工場の門をたたいた若者もいたそうです。また、工場に今まで入ったことがなかったという近隣の方も多かったとか。雇用確保と地域への理解、愛着、自信…。今年は、是非皆さんものぞいてみてください。